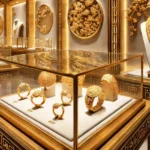日本のデフレ戦略に中国が注目!ユニクロ・ドンキにどう倣う?
中国では現在、消費者物価指数(CPI)が低迷し、2025年2月のCPIは前年比0.7%減少しました。
デフレの影響で消費者の購買意欲が低下し、企業の広告予算が縮小する中、どのようにしてブランドを成長させるのかが課題となっています。
そんな中、中国のマーケティング関係者の間で、日本企業がデフレ期に成功を収めた戦略が注目されています。
日本は1990年代から長期にわたるデフレを経験しながらも、数々の企業が独自のマーケティング手法で成長を遂げました。ある記事では中国企業が学ぶべき事例をいくつか紹介されました。

1.商品ラインの最適化:ユニクロとサイゼリヤの成功
日本のファストファッションブランド「ユニクロ(UNIQLO)」とレストランチェーン「サイゼリヤ」は、デフレ期に商品ラインを大幅に整理し、コア商品に集中する戦略を取りました。
ユニクロはシンプルな基本アイテムにマーケティング予算を投下し、コストを抑えながらも品質を維持。
一方、サイゼリヤはメニューを厳選し、食材管理のコスト削減と厨房の効率化を実現しました。
2.高品質で市場を開拓:セブン-イレブンのプレミアム戦略
日本のコンビニ大手「セブン-イレブン」は、低価格競争に巻き込まれることを避け、プレミアム商品で新たな市場を開拓しました。
2001年には、高級食材を使用した「黄金鮭おにぎり」(約160~170円)を投入。通常のおにぎりより高価でしたが、品質の良さが評価され売上が急増しました。
その後「セブンプレミアム」という自社ブレンドを確立し、高品質志向の消費者を獲得し、売上に大きく貢献しています。
3.デザインとストーリー性で価値を向上:無印良品とドン・キホーテ
「無印良品」は、ミニマルなデザインと環境に優しいコンセプトを打ち出し、ブランド価値を高めました。
一方、日本のディスカウントストア「ドン・キホーテ」は、低価格戦略をエンターテイメント性のある店舗デザインで強化し、消費者の購買体験を楽しいものにしました。
このように、価格が安くても、ストーリー性やブランディングがあれば消費者の支持を得ることが可能です。
4.健康志向と文化的要素の活用:サントリーの無糖ウーロン茶
日本の飲料メーカー「サントリー」は、1981年に無糖ウーロン茶を発売し、「健康志向」という消費者の関心を引きつけました。
さらに、「本場の中国ウーロン茶」といった文化的要素を強調し、日本市場に定着させました。
サントリーは輸入品の価格より手頃な高品質なウイスキーも開発しており、日本市場シェア15%を占めました。
中国ブランドに必要な戦略
経済の取り巻く状況が違っていても、デフレ時代の日本企業の成功例は中国企業にとって参考になるはずです。まとめるとこうなります。
- 集中投資:不要な商品を整理し、主力商品のブランド力を強化する。
- 価値向上戦略:高品質な製品を適正価格で提供し、プレミアム市場を狙う。
- デザインとストーリー性の強化:商品価値を高めるパッケージングやマーケティングを実施する。
- 健康・文化ニーズの活用:消費者が求める健康や文化的価値を訴求する。
こう見ると、デフレが長く続いた日本でも、多くの企業が勝ち残ってきました。時代に合わせた戦略を打ち出せるかどうかが鍵だと言えるでしょう。
現在、日本経済はデフレを脱す状況となってきていますが、加えてAI技術も経営戦略に取り入れなければならない状況でもあります。上述の企業はどんな新たな戦略を取ってくれるか目が離せません。